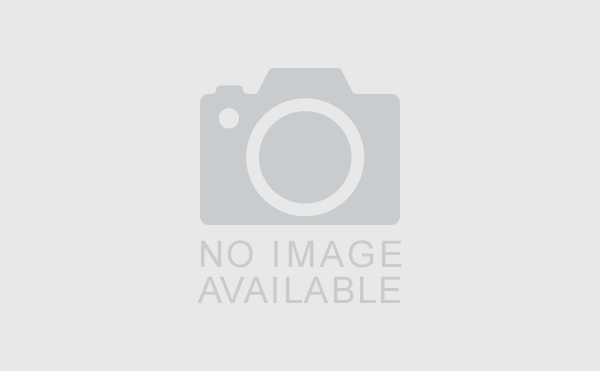分子栄養学は至適量の栄養素を用いて体組成の最適化や抗酸化、代謝の正常化など、生体恒常性を最適化する医学。
・分子を整合する(標準摂取量の数倍)→至適量の栄養素を用いて分子を整合する。分子を整合することで体組成を変化させる。
・補酵素としてビタミンを使う(数十倍~数百倍、メガビタミン)→体内で酵素は基質と結合して反応がおこるが、その際、酵素と基質の親和性は人により大きく異なり、著しく低い場合もある。酵素反応は鍵と鍵穴にたとえられ、ビタミンやミネラルは、鍵が鍵穴に入りにくいときに使う潤滑剤の役目をする。
・動的平衡を保つ(足りないものを足りないだけ補う・数倍)→生体恒常性を保つために足りない栄養素を至適量だけ補う。動的平衡(平衡状態を保つために代謝に必要な栄養素を補う)という考え方。
・受容体活性低下をリガンドの量で補う(数倍)→リガンドとは特定の受容体、レセプターに特異的に結合する物質のこと。統合失調症患者では、HM74A受容体のタンパク発現が著しく減少している。これは、ナイアシンの受容体。つまり、統合失調症患者の脳はナイアシンの感受性が低いため、認知機能を制御するために、多くナイアシンを必要とする。