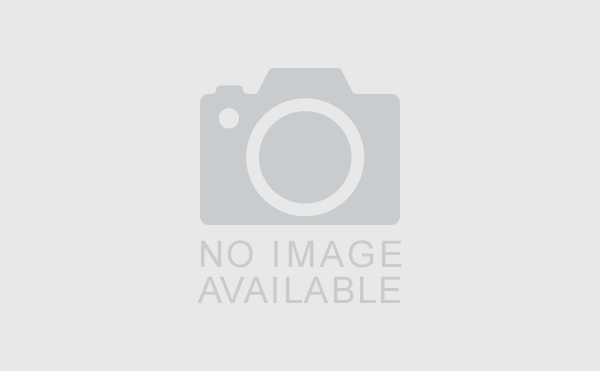酸化ストレスは細胞膜への障害度合いで判断。
間接ビリルビンは溶血、つまり血管の中で赤血球が壊れるということを示す数値。基準値は1.0以下だが、分子栄養学的には0.6以上あると赤血球の壊れる度合いが多いと判断。
赤血球は、酸化ストレスの影響を受けやすく、細胞膜が障害を受けやすい。赤血球はヘムとグロブリンが結合した赤い色素のヘモグロビンを含んでいるが、破壊される(=溶血が進む)とヘモグロビンは遊離し、腎尿細管上皮内でヘムとグロビンに分解される。遊離したヘムによりフリーラジカルが生じ、DNAや脂質を損傷させる有害因子となる。このヘモグロビンは肺から全身に酸素を運搬する役割を果たすが、赤血球自身が酸素消費してしまわないよう、哺乳類の赤血球には核がない。造血の最終段階で脱核が起き、核が排除される。脱核後は、ミトコンドリアミとリボゾームも失う。ミトコンドリアがないため、栄養素も酸素も消費量が減少する。