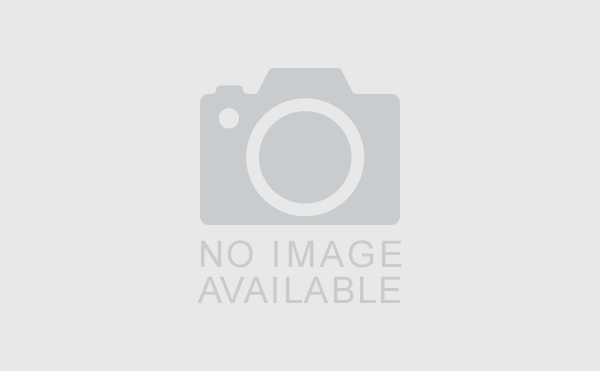細胞内のカルシウムはミトコンドリア、小胞体がほとんどで細胞質には存在しない。それゆえ、通常は細胞内と細胞外の比率は1:10000が維持さスイッチOFF状態。それが、刺激を受けると、一気にカルシウムが細胞質内に流れ込んでくる。このとき細胞内と細胞外の比率は例えば1:1000まで縮まっており、スイッチ ON状態。スイッチがうまく働くためには、常に細胞の中から外にカルシウムをくみ上げておく必要があり、その働きを行うカルシウムポンプを駆動するために体はATPを燃やすためのマグネシウムを大量に消費する。細胞内に入ってくるカルシウムが多すぎると、このポンプ作用が追い付かなくなり、だんだんと細胞内にカルシウムがたまってきてスイッチが入りっぱなしになってしまう。例えば心臓の場合、細胞内カルシウムイオンが心筋細胞の収縮、弛緩のスイッチとなっている。細胞内カルシウム上昇は、心筋細胞が収縮しっぱなしになるため、不整脈や心筋梗塞を起こす。
・カルシウムチャネル→電位依存性チャネル(電位変化、PTHで開口)と伝達物質依存性チャネルがある。
・イオンポンプ→ナトリウムポンプ(Na+/K+ATPase)、カルシウム/マグネシウムポンプがある。カルシウムを細胞内から外にくみ上げる。ATPaseが動くのにマグネシウムが必要。
・カルシウム結合タンパク→カルモジュリン、トロポニンC(細胞内に存在する)
スイッチが入りっぱなしだと、筋肉なら収縮しっぱなしに。
→頑固な肩こり、繊維筋痛症、高血圧、かみしめ、けいれん、こむらがえり、すい臓β細胞は働きっぱなし。
→β細胞が疲弊して糖尿病を起こす。肥満細胞はヒスタミン遊離しっぱなし。
→アレルギー体質に。
このスイッチはほかに、酵素活性や細胞増殖をも調節している。カルシウムの局在異常でスイッチが故障してしまうのがカルシウム・パラドクスといってよい。